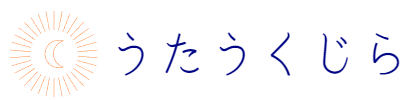2018.12.15公開
戦いの後、未来視の使いすぎで目覚めなくなった久森と重傷を負った矢後くんの話。
矢後くんは夢の中まで入ってきて叩き起こしに来そう。
矢後が目を覚ますとよく見慣れた天井があった。脇に点滴棒、胸元に心電図のコードが繋がれていて、指先に酸素濃度を測る機械が取り付けられている。見るからに鬱陶しい。迷わず、点滴以外の機械を取り外しているといつもの顔が怖い看護師が飛んできた。
「矢後くん、目を覚ましたのね! でも、あなた、それでも重傷者なんだから、取り外さないで欲しいんだけど……」
「別に痛くねえし……」
「一つ間違えたら出血多量で死ぬところだったのよ……本当、生きていて良かったわ」
顔が怖い看護師はホッとしたようにため息を吐いた。
「久森は?」
矢後が意識を失う前、雨の中、久森と二人きりで戦っていたことを覚えている。動きの読めない巨大なイーターで二人で苦戦していた。すぐに久森は上限の三回を使い果たしてしまい、矢後のサポートに徹していた。
戦っているうちにまず、前線の矢後が傷を負った。痛みは感じないから、動きが鈍ることもなく、平気で戦っていた。しかし、痛みを感じないだけで出血が止まるわけではない。事態を早く収めようとした久森は四回目の未来視を試みる。かなり無理をしていたようだが、矢後としては勝てばいいので、気には留めなかった。
それから、六回目の未来視で風雲児の二人はイーター退治に成功した。その頃には二人とも身体が限界でまず、力の使いすぎで久森が倒れた。それから、矢後も出血多量で意識を失った。そして、今に至る。
久森は怪我自体は矢後よりずっとマシだった。勿論、起きているだろうと思っていたのだが、看護師の顔は暗い。
「あいつ、もう起きてるだろ?」
「……あのね、矢後くん。まだ久森くんは目を覚ましてないの」
「は?」
看護師の一言に矢後は少しだけ目を見張る。
「これでもあの戦いから三日は経ってるわ。でも、目を覚ます気配がないのよ。原因は先生にも分からないの」
はあ、とため息を吐いた看護師の横顔を見て、無性に腹が立った。理由なんて分かっているだろう。未来視の力の使いすぎだ。本人が言っていた限度の倍は使ったのだから、その分身体に負担があったっておかしくない。それを治すのが医者の仕事だろう。
「ったく……マジでここにはヤブしかいねえな……」
精一杯の苛立ちを込めた矢後の呟きに看護師は静かに目を閉じるだけだった。
看護師に案内された個室で久森は静かに眠っていた。目覚めたての矢後と同じくらいの装置を取り付けられていた。怪我自体はやはり、脇腹を抉られ、肩に爪が刺さった矢後よりずっと浅い。それでも眠り続けているのはやはり力の使いすぎが原因なのだろう。
――― 未来視の力を使っていいのは一日に三回だけにしてます。それ以上使うと自分でもよく分からないことになってしまいます……。三回目でも結構キツイんですけど、それ以降はもっと頭が痛くなっちゃうんで。
未来視について、そう説明されたことを覚えている。当時の自分は耳くそをほじりながら、半ばぞんざいに聞いていた。
自分たちの勝利のために頭痛と身体の痛みに耐えて、限度の倍の未来視を行使したと思うと、世間的にはなんとも目頭が熱くなる話だろう。しかし、矢後にとっては微塵もいい話ではなかった。
「オラ、起きろ!」
「ちょっと、矢後くん?!」
いきなりベッドを蹴り出した矢後を見て、看護師が目を見開く。馬鹿力に蹴られてもベッドは変形していないし、久森も眠り続けているだけで起きない。
「起きねえのかよ……」
「そういう簡単な問題じゃ……あっ、ちょっと行ってくるわね。その間、久森くんを殴ったりしちゃダメよ」
看護師のPHSが鳴り、久森の病室に矢後を置いて、彼女は去って行った。
「……お前はもっと、自分勝手な奴だろうが……何自己犠牲に目覚めてんだよ」
矢後が見る限り、久森晃人は自分勝手な男だった。自分勝手に矢後に小言を言い、寝ていれば叩き起こしてでもパトロールに引っ張っていく。趣味のゲームに没頭していれば、矢後の言うことさえ無視をする。さらに休日は矢後が気まぐれに電話をかけても出ないことしかなかった。
そんな久森が矢後のために生命を賭けるなんてことがあるだろうか。
「自分勝手なのはお前だろう、矢後」
「……頼城」
やたら小気味のいい靴音を鳴らしながら現れたのはラ・クロワ学苑の頼城であった。紫色の上品な制服に身を包んだ彼は矢後の発言を聞いて、呆れたようにため息を吐いた。
お互いいけ好かないと思っている同士である。当然、出会えば剣呑な雰囲気にもなる。
「何しに来た……」
「東エリアのパトロールの報告だ。一応、学校リーダーであるお前にも伝えておくべきだと思ってな」
「お前らが仲良く入院しちまったからな、東エリアは交代で合同パトロールしてんだよ」
「心配するな、今のところ、大型イーターは出ていない」
白いブレザーを羽織った、白星の武居が気怠そうにぼやき、その隣で崖縁の戸上が微笑む。彼らの他に斎樹と御鷹がいた。久森と仲が良かった二人だ。
「んなもん、俺は今日からでも復帰できるからよ。もういらねーよ」
「いや、そういうわけにはいかないだろう。痛まない体でも抜糸するまでは安静にしているべきだ」
医学博士の称号を持っているだけあって、斎樹は冷静に忠告してきた。
「俺と巡くんは頼城さんたちについてきて、晃人くんのお見舞いに来たんです。今日は起きてるかなーって思ったんですけど……」
あ、でも、矢後さんは起きてて良かったです、と付け加えて、御鷹が微笑む。ついでなのが丸分かりである。
「俺はついでかよ」
「……あ、すみません……」
「御鷹、正直に言わなくてもいいんだぞ」
「……」
「あの、晃人くんに声かけてもいいですか?」
「俺に訊くもんじゃねえだろ。どうせ寝てんだから、好きにしろ」
矢後は久森の親でも兄でもないのだが、矢後のお墨付きをもらった御鷹と斎樹は久森のベッドに向かって行った。
「今日もやっぱり起きてないなぁ……。おーい、晃人くん。今日で三日目だよ?」
「顔の血色もいいし、呼吸も規則正しいんだがな……。あまりみんなに心配をかけるな、早く起きろ」
「あまりの俺の美しさに目覚めると思ったんだが……。起きて、矢後にぶたれたり、困ったことがあったら、頼城さんを頼りなさい!」
「いや、お前はうるせえよ」
「何故起きないんだろうな」
知らないうちに五人でベッドを取り囲んでいる。今、久森が起きたら、動揺のあまりにベッドから飛び出すことだろう。しかし、そんなこともなく、気にせず久森は眠ったままだ。
「そういや、斎樹、お前、医学博士なんだろ? 久森のこの症状、分かんねえのかよ」
突然矢後に訊ねられて、斎樹は一瞬目を丸くしたが、すぐに首を横に振った。
「……そんなこと言われても、俺にも分からない。MRIにもCTにもかけたそうだが、身体的には問題はなかった。起きないのはきっと、あの能力の問題だ。未来視自体、医学的にも科学的にも立証されていないから、我々が理解できる範疇ではないんだ。……あんたも含めて、風雲児は非科学的すぎる」
「……そうかよ。世の中にはヤブ医者しかいねえってことだな」
斎樹の言ったことはよく解らなかったが、どんな高名な医者でも久森を治せないということはよく解った。
「……ったく、めんどくせえことになりやがって……。ぜってぇ起きたら泣かす」
「矢後さん、そんな言い方……」
「御鷹、そう言ってやるな。あの二人の問題なのだ」
矢後のぞんざいな言い方に意見しようとした御鷹をそっと頼城が止める。
「俺たちの何倍も久森と顔を合わせているからな、きっと泣かすのも矢後なりの愛情表現だ」
「泣かすのが……? それ、愛情が歪みすぎだろ。ていうか、それは愛情なのか?」
淡々とおかしなことを言う戸上に武居がツッコミを入れる。
「……好き勝手言いやがって、俺と久森にそんなもんねーよ。お互い、好き勝手にやってただけだ。仲間なんて感情、これっぽっちもねえ」
「ある奴ほど言うやつだな」
「ああ、間違いない」
「そうでしたか……すみません」
「お前ら、俺がキレる前にもう帰れや」
コソコソ話している頼城と斎樹と御鷹を睨むと他の二人は肩を竦めたが、頼城だけは俺は解っていると言った顔で矢後を見つめて来た。殴り飛ばしてやろうか。
「今日はお前だけでも元気にしていて良かった。お前たちが入院している間、江波区のことは俺たちに任せてくれ」
「この頼城の名を持って、東エリアの安全を保障するぞ! お前は安心して、ベッドに臥せっているがいい!」
「……まあ、二人とも身体は早く治せよ」
上級生三人(武居は二年だが)が口々にそう言うとその後に二年の二人が続く。
「今日は二人のこともよく解らずにおかしなこと言って、色々とすみませんでした。でも、元気そうで良かったです。晃人くんが起きたら教えてくださいね」
「心療内科の範疇は専門外だが、久森の症状のこと、俺なりに調べてみよう。だから、抜糸が済むまでは安静にしていてほしい。きっと、久森もそう言うだろう」
――― お腹縫われてるくらい重傷なのになんでうろうろしてるんですか、抜糸まで安静にしてるもんでしょう、普通。
斎樹の一言と共に久森の小言が聞こえてくるようだった。平気でそんなことができてしまうあたり、よほどヤキが回っている。
「……おう」
「じゃあ、明日も来るからな」
ぞろぞろ帰っていく五人を見送る。帰っていく彼らも賑やかで「そういえば、パトロールの報告してねえじゃねえか」などと武居が大声で騒いでいる。そういえばそうだ。だが、使命感を持って戦っているわけではない矢後にとってはどうでも良かった。
なんとなくベッドで寝ている久森の顔を見た。固く閉じられた目から涙が一筋溢れていた。どんなに危篤症状の人間でも耳は聞こえているから、最期のときまでみんなで声をかける、という話を聞いたことがある。
「……俺が泣かす前に泣いてどうする」
溢れた涙を隠してやるように指で拭ってやった。
***
次の日、うっかり身の回りの品を持ってきた久森の両親と遭遇してしまった。二人とも久森の病室から出てきた矢後を見て、あからさまに嫌な顔をしていた。当然といえば当然である。明らかに不良の男が自分の息子の病室から現れたのだから仕方ない。
「あなたが矢後くんね……?」
久森とそっくりの母親が怒りを露わにして、紙袋を取り落す。そして、そのまま矢後に平手打ちを喰らわせてきた。まったく痛くはないが、息子と同じ色をした目がこちらを睨みつけてきて、まるで久森本人に睨まれているような気分になる。そのまま、二の腕を掴まれて、まくし立てて来る。
「どうして……どうして、晃人をヒーローになんてしたのよ! 私たちに断りもなく、あんなことするような子じゃなかったのに! ヒーローになんてならなければ、こんなことにはならなかったのに……!」
「母さん、やめないか……」
優男の父親が逆上した母親をそっと止める。しかし、矢後を見る目は母親と同様だ。
「晃人がヒーローになったなんて知ったのは、突然だったのでね。妻は少し混乱してるんだ。私だって混乱をしている。家では内向的であまり外に出て遊ぶ方ではなかったからね。内気で聞き分けのいい子だった。未来視の力が云々なんて言われたけれど、そんな非科学的な力、あの子が持ってるわけないだろう?」
「あなただけじゃない……。この病院の先生もどうかしてるわ……あの子が眠ったままの理由も分からないなんて……」
「そりゃ仕方ねえよ。この病院にはヤブ医者しかいねーからな」
怒りに震える母親に燃料でも注ぐかのように矢後が笑う。
「話を聞けば、あなたが晃人をヒーローにしたそうじゃない。このままあの子が起きなかったら、どうしてくれるのよ! どうしてくれるのよ!!」
燃料を与えられた母親はまた散々喚き散らし、そのまましゃがみこんで泣き始めた。父親が妻の取り乱しように困っている。
「すまねえが、俺にはどうもできねえわ。でも、あんたらの話はちょっと面白くて笑うわ。家と俺の前じゃ、あいつの態度もだいぶちげえんだなぁ」
「は? どういうことだ?」
「あいつは余命宣告されてる先輩に容赦なく文句言って、雑用押し付けるような奴なんだぜ? ああ、何度か無視もされたな」
「あの子はそんなことするような子じゃ……」
「それじゃ、あいつは親の前でも気ィつかって、猫かぶってたってことだな。あんたらが嫌がるから未来視のことも誰も話さずに隠して、こそこそ自分も隠れて生きてきたわけだ。あんな陰キャになっても仕方ねえよなぁ……」
鳩が豆鉄砲を喰らったような顔をして黙っている久森の両親の顔を見回す。しかし、泣いていた母親が再び立ち上がり、また矢後の頬に平手打ちを喰らわせてきた。避けずに甘んじて受け入れる。何せ、痛くないのだ。痛がる素振りも見せない矢後を母親は怯えたように見上げていた。
「痛くねえよ、そんなの。生まれつき、痛みを感じない体なんだわ、俺」
「そ、そんなことあるはずない……だろ?」
父親がまるで化け物、とでも言いたげな顔で青ざめている。しかし、彼らの息子もまた、彼らにとって化け物の一人なのだ。
「あんたら、自分の息子にもそんな目、向けるつもりなのか?」
両親共々言葉を失う。彼らだって、息子が未来視の力を持っていて、ヒーローをやっているとかいう重大情報を突然知らされて、混乱しているのは、矢後でもよく解っている。それでも、自分の子供に対して、化け物だなんていう感情は持たないでやってほしかった。
茫然自失としている久森の両親を置いて、矢後は自分の大部屋の病室に戻ることにした。
病室に戻るとベッドの周りのカーテンが開いていて、母親と姉が来ていた。矢後が戻って来たのを見つけるなり、母親がベッドサイドテーブルに置いた紙袋を指差した。いつも入院するときに持たされるものだ。
「勇成、いつもの入院セット置いといたからね」
「あんた、また入院してんの。昨日、いきなりあんたが三日間の意識不明から目覚めたって連絡入ってびっくりしたんだからね。家にいるより、病院にいる方が多いんじゃないの? たまに入院サボってるし……あんまり、お母さんに心配かけてんじゃないよ」
「うるせえ、ババア二人」
髪をいじりながら矢後がぼやくと姉が「はあああ?!」と怒り出した。姉はまだ矢後に色々言う方だが、母親は余命宣告されている矢後を気遣って、あまり何も言わない方だった。久森が親に気を遣っているなら、矢後は親に気を遣わせているのだろう。
「あの大人しい子は来てくれたの?」
「あ?」
「勇成と組んでヒーローやってる子よ。勇成の友だちにしては大人しい子だったから、よく覚えてるの」
「ああ、あのカワイイ子? あの子もヒーローなんて信じられないよね」
「……あいつはまだ個室で眠ってんだよ。ちょっと俺、イライラしてっからよ……さっさと帰れ、ババア共」
ベッドに座るとわざと大きな音を立てて、ベッドサイドテーブルを叩く。母親はビクッと肩を震わせたが、姉は矢後を睨んでいる。
「お母さん、行こ?」
戸惑っている母親の二の腕を掴んで、姉はのしのし病室を去って行った。その対応が正解だ。隣のベッドの男がカーテンの隙間からこちらを見ていたが、矢後が睨むとすぐ引っ込んでいった。
昨日みんなに言われた通り、ベッドで大人しく寝ていようかと思ったが、今は機嫌よく寝れそうもない。ベッドから再び立つとその足は 病院の屋上へ向かっていた。
病院の屋上は昼の時間帯はリハビリ庭園として解放されていて、フェンス内を老人たちが歩き回っている。矢後はその端にあるベンチに横になった。
リハビリに精を出す老人たちに興味はなく、ただ、空を見つめる。トンビが空をぐるぐる旋回していた。
――― 鳥は自由だなぁ……。
いつか、久森が鳥を見ながらぼやいていたことを思い出した。なんともありきたりなことを言うものだから、思わず吹き出してしまった記憶がある。
鳥は自由だ、と羨ましがっていたが、彼は鳥になりたいわけじゃない。真になりたいものはきっと違う。休みの日は人との接触を完全に遮断して、家に引きこもるあたり、きっと貝になりたいのだと思う。久森の心は海に沈む貝のように、常に固く殻を閉じ、外敵から身を守っている。それはきっと、自らの親に対しても、矢後に対してもそうだ。
「ヒヒッ、黄昏てんな。風雲児の『死神』」
影が顔に掛かると思えば、制服姿の崖縁の浅桐が矢後を見下ろしていた。
「おお、何だ? 崖縁の『悪魔』。ジジイとババア観察にでも来たのか?」
「ここはオレの高みスポットの一つなもんでなァ。昼間に今に死にそうなジジイとババア観察も悪くねえなとは思うがよ。それにしても、随分不景気なツラしてんじゃねーの。今にも壁の一つはぶっ壊しそうだ」
「お、いーねぇ、それ……スカッとしそうだわ」
なかなか物騒なやりとりをしているが、実際にやる気はない。これ以上、この病院で何かやらかせば、きっとあの怖い顔をした看護師がめんどうだろう。
「『死神』がガチの死神になっちまうとはなぁ……」
「あ?」
「お前の相方の未来視が使えるモブ、とうとうイカれちまったじゃねえか。一体、どんな無理をしたかは知らねえが」
「俺は関係ねぇ。あいつが勝手にやりすぎただけだっつの」
「あいつを人体強化する気はねえか? 未来視のギミック、天才のオレがバッチリ確かめてやるからよ。勿論、お前も」
「俺が勝手に決めることでもねえだろ、それ。別にあいつの未来視のギミックとかどうでもいいし。便利だから使ってただけだし。それにあいつも俺も今で満足してんだわ。これからも人体強化なんてするつもりねーよ」
勝手に人体強化をされて、身体の一部を変えられてしまったら、久森も嫌だろう。
「あいつは一生眠ったままかもしれねえぞ? そんなのお前にとっちゃ、最悪のバッドエンドじゃねーか」
「そのうち、寝るのに飽きたら起きるだろ。バッドエンドもクソもねえよ」
「そーいうもんなんかねぇ? あいつの眠りを覚まさせてくれる王子様がいればいいんだがなァ」
「あいつも男なんだし、そこはお姫様にしといてやれ」
「違いねェ」
ヒヒッ、と悪役じみた笑い声で浅桐は笑う。眠り姫はキスで目が覚めるだなんてよく言ったものである。よくあんな小さい接触で目を覚ませるものだ。矢後なら鍋とおたまを必要とするところである。
「俺にとっちゃ、あいつが起こしてくれる王子様なんだろうな……」
どこでも眠ってしまう矢後を叩き起こすのは久森の仕事だった。「起こして」と目覚まし時計代わりに使うこともある。起きるときはいつも不機嫌でそのとき一番近くにいる久森に当たり散らすこともあった。胸倉を掴まれても、「いや、矢後さんが起こせって言ったんですけど」と平然と返す随分肝の据わった王子様だった。
「こいつァ、おもしれぇ。『死神』は眠り姫でもあったわけか」
「まあ、似たようなもんじゃね? 今はその王子様が寝てるわけなんだがよ」
昏々と眠ったまま目覚めない久森の顔を思い出す。
「王子様が眠り始めたとき、眠り姫はどうすんだァ?」
「……知らねえわ、そんなん。お姫様なら、起きるよう祈ることしかできないんじゃねえの?」
お姫様ならそうである。しかし、矢後はお姫様と似たようなもんでお姫様なわけではない。優しく、起きるように祈ってやるなんてことは絶対にしない。
***
天気は生憎の大雨、視界が不明瞭な中、お互いの得物だけが光を放っていた。
「ずいぶんやってくれんじゃねえの……」
黒い戦闘服が水を吸って、重い。だが、矢後の脇腹は先程、イーターに抉られたばかりで下の白いシャツに赤い染みができている。傷口もなかなかグロい。それでも平常心で立っていられるのは、矢後が痛みを感じない身体であることと戦闘狂であるからに他ならない。そのうちのどれが欠けても、この時点で倒れていることだろう。
「矢後さん、その傷で無茶ですよ! 一度撤退して、応援を呼びましょう」
「ハッ! 冗談! こんなにおもしれぇ奴そういねえからな。絶対俺が仕留める!」
「あー、そうですねそうですよね! 矢後さんならそう言うと思ってました!」
はあ、といつもの深いため息を吐いてから、こめかみに手を当てる。
「矢後さんがそんな無茶するなら、僕も多少無茶をします。もう一回視るんで、ちょっと時間稼いでください」
「へえ、三回以上できんじゃん! じゃあ、頼むぜ!」
イーターの伸縮する腕が何本も二人を攻撃しようと迫るが、矢後がそれを大鎌で薙ぎ払う。だが、また伸びてくるからキリがない。矢後の背後で未来視をしている久森は何度か頭を押さえて呻いていたが、じきに顔を上げた。
「矢後さん、今度は右から来ます! 隙ができた左を攻撃してください」
右からの攻撃を矢後が軽やかな動作で飛び跳ね、避けると左を攻撃しようと大鎌を振り上げ、左脇を裂いた。グアアア、とイーターがおぞましい悲鳴をあげる。
「もう一回、この調子で行きましょう! うっ……う、今度は上から来ま……ああっ!」
五回目の未来視をしたものの、見切れなかった攻撃があったらしい、伸びた右腕が久森を弾き飛ばしていた。地面に叩きつけられ、うずくまる。
「おい、何やってんだ……!」
「あ、ぐ……あいつ、回遊種のくせになかなか動きが読めない……。あの、僕、今からものすごい無茶をします。矢後さんも手伝ってください」
矢後が駆け寄ると肩を押さえながら、久森は起き上がった。そして、術式のグローブから得物の糸を具現化させるとあやとりの要領で引っ張った。
「なんかあんのかよ」
「もう脇腹抉れてるんですから、今更どこ傷ついてもいいですよね? 矢後さんにはオトリになってもらいます」
「先輩遣いの荒い奴だな、ちったぁ怪我してる先輩を労われや」
「僕が未来視をしながら、隙を見つけます。見つけたら声をかけるのでそれに合わせて鎌を振り上げてください。僕がその間に仕留めるので……あ、トドメは矢後さんに置いといたほうがいいですかね?」
「ハッ、しゃーねえ! 譲ってやんよ! その代わり、しくるなよ!」
「外さないよう、祈っててください」
イーターが少しずつ動き出す。久森も目を開けたまま、未来視を始めたようで普段より目の色が明るく見える。その表情は痛みに耐えているのか、固い。
イーターの攻撃を数回避けてから、「今です!」という久森の声がした。高く跳躍して、大きく大鎌を振り上げるとイーターの爪が肩に突き刺さる。痛くはない。矢後に気を取られたイーターを久森の糸が包み込む。久森は外さないよう祈っていてくれと言いながら、やることはキッチリやる男だ。無論、矢後は祈ったことなどない。
「俺らの勝ちだ!」
「僕らの勝ちだ!」
二人の声が合わさったところで久森が強く糸を引き、イーターが断末魔の声をあげた。
無事にイーターを始末して、安堵でもしたかのように久森は前のめりに崩れ落ちた。普段三回しかしないものを六回もしてしまったから限界だったのだろう。矢後もさすがに出血多量には勝てず、意識を失った。