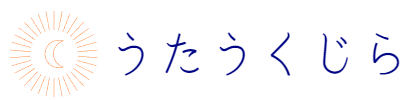2019.01.11
矢後くんが心肺停止するけどまた復活する話。さすが不死鳥の矢後だぜ!
後半は風雲児無双です。悪い顔して舌打ちする久森大好き。
微妙に「夢の中へ」と繋がっている気がする。
霧谷の手を握り、目を閉じる。脳裏を彼らがこれから出会うであろう異形とその戦いが過ぎる。とても楽な戦いではない。内容は絶望的だと言っていい。
「どうだ、久森」
霧谷の肩に手を置いた頼城が訊ねてくる。不思議な彼らの行動に霧谷は怪訝そうにしている。
「キツイ戦いになりそうです。どれもこれもCⅡ、CⅢ級のイーターが飛び出してきます。でも、ラ・クロワの皆さんなら大丈夫ですよ、きっと」
「そうだといいんだがな……本当は絶望的なんだろう?」
久森の未来視に斎樹が怪訝そうに訊ねてくる。
「……うん。でも、もうやるしかないから。少しでもいい風に言っておきたかったんだ」
「久森なりの優しさなんだろうが、本当のことははっきり言っておいてくれた方がいい。その方がこちらだって気が引き締まる」
「そっか、余計なお世話だったね。ごめん」
「さっきから何の話してるの? そろそろ手を離して欲しいんだけど……」
「ああ、ごめんね、柊くん。勝手に未来を視ちゃって。先に言っちゃうとモヤモヤしちゃってダメだから……」
「なんでそんな勝手なこと……」
勝手に未来を視られたと知った霧谷は久森を睨む。当然と言えば当然だ。勝手にやられると何でも気持ちが悪い。
「俺が頼んだ。さっきは正義に頼まれて、三津木少年の未来を視ていたな」
「やっぱり紫暮のせいだった」
久森を睨んでいた青い目が今度は頼城に向けられた。
「同じ術式だと立ち位置がそんなに変わらないから状況を把握しやすいんですよね。まあ、伊勢崎さんみたいなアタッカータイプだとまた別なんですけど」
「白星・崖縁・愛教の本隊はどうだった?」
「頼城さんたちとそんなに変わりません。人数が多いだけ、戦いはマシかも知れませんが……」
今回の作戦は白星を中心とした本隊とラ・クロワと風雲児の別働隊に別れて行われることになっていた。指揮官曰く、最後の戦いになるらしい。
「本当は僕も行くべきなんでしょうけど……すみません」
「いいや、構わない。できるならば、後から追いかけてくれればいい。それに……たとえ矢後でも一人は寂しいだろう。傍にいてやってくれ」
頼城が微笑みながら、久森の肩を叩く。矢後の名前を出されるとこみ上げてくるものがあった。なんとか堪えながら、頼城に深々と頭を下げる。
「ありがとうございます……。落ち着いたら、僕も矢後さんを連れて、追いつきますから」
「そうしてくれるのなら有り難いが、無理はしなくていいからな」
「いいや、絶対行くよ」
斎樹の気遣いに首を横に振ると背後の集中治療室を振り返る。そこで今、矢後は医者たちによる懸命な治療を受けていた。
最後の戦いを目前にして、矢後が血を吐いて倒れたのは今朝のことだ。それからずっと集中治療室にいる。しかし、作戦決行を止めることはできず、別働隊はラ・クロワの面々だけで動くことになり、久森は一人八草中央病院で矢後に付き添うことになった。もしかしたらこれが最期かもしれない、そういうとき、一人でも看取る人間がいないと可哀想だと察した指揮官のはからいであった。
***
時間になり、戦地へ赴いていったラ・クロワの面々を見送ってから、久森は再び集中治療室の前のベンチに戻った。
「……矢後さん」
今回が本当に最期なのではないか。不安に押し潰されそうになりながら、集中治療室に入っている矢後を窓越しに見守った。
矢後が死ぬかどうか、矢後に触れれば視える。今は意識がないから、視られるという認識もないからよく視えるだろう。だが、とても怖くてできなかった。
「久森くん、ちょっと来て!」
治療室の内部が騒がしくなり、中の看護師が久森を呼びつけた。
「今、矢後くん、心肺停止なの! 声、かけてあげて! 早く!」
「はい!」
断る理由もなく、久森もマスクや手袋などの身なりを整えて、治療室に入ると心電図の機械がピーーー、と心臓が動いていない音を響かせていた。それを見ただけで久森は血の気が引いた。心臓がバクバクして、足元がおぼつかない。目眩もする。幾度もの死亡フラグを己でへし折ってきたあの矢後が死ぬ。まるで、現実ではないかのようだ。
医者が何度も心臓マッサージを施している。心臓を穿たれるたびに心電図の線が何度も脈打った。
「聞こえてるから、声をかけてあげて!」
看護師に言われて、久森は震える脚でなんとか矢後の傍に駆け寄った。
聞こえてるから。そういえば、以前にもこういうことがあった。あのときに目覚めなかったのは久森の方だった。力の使いすぎで一週間昏睡状態に陥った久森を目覚めさせたのは夢の中まで乗り込んできた矢後であった。眠っている間も何度も、何度も矢後は声をかけてきていた。
(僕には全部聞こえてた)
貝に閉じこもっていたから、小さくだったが、自分の周りで交わされる会話も、矢後のかけてくる声も、すべて聞こえていた。
(きっと、矢後さんにも聞こえるはずだ……)
しかし、久森には矢後のように夢の中まで乱入するような非常識さはない。だから、自分らしく、静かに糸を垂らすことにした。
「矢後さん、起きてください。このまま起きないと本当に死んじゃいますよ、矢後さん!」
そっと矢後の耳元で声をかける。反応はない。まだだ。さらに奥へと糸を垂らす。
「僕は別にそれでもいいんですけどね。そこんとこは矢後さんの好きにすればいいと思います。でも、戦場はそうもいかないんですよね。術式の僕一人じゃどうにもできない。矢後さんを盾にしないと僕は前に進めないんですよ。あなたが好きに暴れて、僕が後ろからサポートする……今までずっとそうしてきたから、それで慣れてしまったんですよね。今更変えられないんですよ」
学ランの裾を掴み、久森はそう続けた。相変わらず医者は心臓マッサージを続けている。なかなか心音は定着しない。糸を垂らし続ける。
「ねえ、聞いてます? あー、矢後さん、たまに聞いてないことあるからなぁ……。矢後さん……矢後さん? 聞いてくださいよ。このままじゃ、本当に死んじゃいますよ? いいんですか?」
何度心臓マッサージをしても定着しない心音に医者の目に諦めの色が見え始めた。医者だけではない。看護師たちももうダメだ、とばかりに目を伏せている。
「あの子、余命宣告されてるけど、順調に更新してた子だよね?」
「まあ、いつ死ぬか分からなかったしなぁ」
看護師たちは久森に聞こえないよう話しているのだが、しっかり聞こえてしまっている。久森の汗ばんだ手がギュッと拳を作る。このままじゃ、ダメだ。
「これから、大きな敵が待ってるっていうのに、こんなところで死んでいいんですか? これからもっといっぱい、大好きな派手な喧嘩ができるのに……。慎くんも柊くんも視たらすっごいのに会ってました。これ見たら矢後さん喜ぶだろうなーって思いました。僕はやですけど。ねえ、矢後さん……」
頭の中を走馬灯のように矢後と戦ってきた日々が駆け巡る。普段は寝ることと食べることくらいしか考えていないくせに、戦いのときだけは目を爛々と輝かせ、イーターの返り血を浴び、自らも傷だらけになりながら、やたらと元気に戦場を駆け回っていた。戦うことこそが己の人生だとばかりに。そんな人間にこんな平穏な死が似合うだろうか? そんなの絶対に許せない。
「これでいいのか?! こんなところで死んでいいのか?! 矢後さんがこんなところで死ぬのなんて僕が許さないからな! いい加減起きろ! いいのか? 本当に死ぬぞ……? いいのか?! 矢後勇成!!!!」
気がつけば叫んでいた。相手は先輩なのに敬語までかなぐり捨てていた。
限界まで糸を垂らすと誰かがそれを掴む、確かな感触がした。
医者の心臓マッサージか、久森の叫びか、どちらかが功を奏したのか、ピッ、ピッ、と心電図が規則正しい心音を立て始めた。医者も看護師も呆然と久森の方を見ている。
「き、奇跡だ……」
「どうなってるんだ、一体……」
医者たちは首を傾げている中、久森の手首が突然引っ張られた。驚いて下を見るとさっきまで死んでいたはずの矢後が目を開けて、久森を睨んでいた。
「……うるせえよ。ここをどこだと思ってんの?」
「それ、絶対矢後さんに言われたくないです……」
「……ずっと聞こえてたっつーの」
「じゃあ早く起きてくださいよ……本当に死んじゃうかと思ったじゃないですか……」
酸素マスク越しに聞こえる掠れた声にいつも通り返す。声はいつも通りだろうか。涙声になっていると悟られたら、すごく恥ずかしい気がした。
「今、ここにいるヒーローは風雲児の君たちだけなんだ。他のみんなは今頃、最後の敵と戦っているだろう」
矢後の退院に合わせて病院にやって来た神ヶ原は風雲児の二人の顔をそれぞれ見た。彼の手には大小二つのアタッシュケース。
病院の外は晴れていて、爽やかな風が吹いている。平和そのものだ。今、世界の裏側でヒーローたちが戦っているなんて誰も夢にも思わないだろう。
「君たちにこれを渡そう」
神ヶ原が小さい方のアタッシュケースを開けると七十一と七十三の刻印が入ったリンクユニットが入っていた。いつものものと色は同じだが形が違う。
「これは……?」
「君たちの能力と身体に合わせた新しいリンクユニットだ。通常の戦闘服より倍の威力を出せる」
「へえ、いーじゃん。それ、くれんの?」
「そのつもりだ。でも、これを使えばもう二度と普通の人間には戻れないだろう。特に君たちは。生まれたときから持っていた能力が身体とよくリンクしているからね。その分、副作用も倍になる。きっと、君たちはこれからもこれを手放せなくなる。それくらいの中毒性があるんだ。本当なら僕も君たちのようなこれからがある高校生には使わせたくない……。嫌なら断ってくれていい。僕も……」
「いいぜ、別に」
神ヶ原がすべて言い終わるまでに矢後がリンクユニットを手に取った。隣で見ていた久森が目を丸くしている。
「矢後くん、僕は君たちの身体が心配で言ってるんだけど……」
「どうせ初めからぶっ壊れてんだから、さらに壊れたところで一緒だろ。生憎、俺もこいつも生まれたときから『普通の人間』ってやつじゃないもんでな。んなの今更なんだわ」
「えー! 僕もなんですか? 僕、いいとか言ってないんですけど……はあ」
矢後の半ば強制的に久森を巻き込むような発言に彼はため息を吐く。そして、七十三番のリンクユニットを手に取った。
「仕方ない。もうここまで来たらとことん付き合いますよ」
「ホント話早くて助かるわ、こいつ」
決心した二人を前にしても、神ヶ原の表情は晴れない。
「本当にいいの? もしかしたら死ぬかもしれないんだよ?」
「……上等! こちとら、ずっと余命宣告されてんだ。それなら、こっちから地獄に行ってやらぁ!」
拳を叩きながら、矢後が吠える。その隣で久森は再び狼狽えた。
「え、僕、そんなとこまで付き合わされるんですか?」
「あ? 何?」
「はー……はいはい、分かりました。地獄の底までついていきますよ」
久森が何度目か分からないため息を吐くと神ヶ原がさらに制止の言葉をかける前に矢後がリンクユニットを割る。それに久森も続いた。光に包まれた彼らは背中に風雲児の文字と桜吹雪の和刺繍が縫われた上位戦闘服姿に変わる。
「君たちは本当に仕方がないね。久森くん、矢後くんのことは任せたよ」
「はい」
「あと、これをみんなのところに届けて。みんなのための上位戦闘服のリンクユニットだ。使う前にはちゃんと、さっき言ったことを訊いてね」
「分かりました。必ず渡します」
神ヶ原に渡されたアタッシュケースを抱えると久森は矢後と同じ、敵の根城がある方角を向いた。そこでみんな、苦戦を強いられているのだろう。
より強力な敵がいるだろうが、不思議と怖くなかった。
「行くぞ、久森」
「はい」
「風雲児、出る……!」
二人は白いスカーフを翻し、最後の戦いへと走り出した。
***
最後のリンクユニットの接続が切れ、傷だらけの制服姿で斎樹は倒れた。術式の霧谷はとうの昔に意識を失っている。頼城だけがかろうじて、敵と対峙していた。剣とイーターの爪がチリチリ音を立てて拮抗している。
(もう終わりなのか……?)
ここで頼城があのイーターと勝ったところでまだまだたくさんいる。不可能を可能にせんばかりの勢いの頼城であってもいずれは限界が来るだろう。それも近いうちに。それ以降は一体どうなるのだろうか。こういうときにこういうことを考えてしまうから、理屈っぽい自分はダメだ。そう思って、斎樹は一人自嘲した。
イーターの爪を振り払い、一刀両断したところでとうとう頼城の接続が切れた。
「おのれ……もう終わりだと言うのか……。俺はまだ……」
斎樹や霧谷と同じように傷だらけの制服姿に戻った頼城は片腕を押さえ、まだ控えているイーターの大群を睨む。なるほど、久森が視た通り、事態は絶望的だ。
(結局、久森は来なかったな……)
他のメンバーの倍近く、矢後と顔を合わせ、面倒を見てきたからこそ、喪ったとき、その心の傷も深いはずだ。だが、こんなところ、来なくて正解だったのかもしれない。もう終わりなのだ。自分たちも、この世界も。
大型イーターが斎樹目掛けて、爪を振り下ろそうとしている。いよいよか。観念して目を閉じたその瞬間であった。
「まだ、終わってない」
どこからか光状の糸が数本伸びてきて、イーターを拘束し、動きを止めた。その直後、目にも留まらぬ速さで何者かが斎樹とイーターの間に割り込み、イーターを巨大な鎌で斬り裂いた。
そんな大鎌を使う人間を斎樹は一人しか知らない。まさか、嘘だろう。そう思って、目をよく開く。白いスカーフがたなびく下に光り輝く『風雲児』の文字が見えた。茶色い髪だから久森ではない。
「ホント、情けねーな。お前ら」
黒いヘアバンドを引き上げ、振り返ったその男は紛れもなく死んだはずの矢後勇成だった。死んだはずなのに大鎌を片手に不敵に笑っている。斎樹だけではない。頼城も、霧谷もまるで幽霊を見たかのように矢後を見ている。
「もー、矢後さん、先さき行かないでくださいよ。仕損じの処理、大変なんですから!」
矢後に続いて、アタッシュケースを小脇に抱えた久森も現れた。一体どうなっているのだ。ラ・クロワの三人が呆然としている横で二人は普段通りのやりとりをしていた。
「それに……」
はー、とため息を吐いてから久森は矢後の方へと糸を放った。グローブから鋭い針のように伸びた糸は矢後を狙っていた中型イーターを串刺しにしていた。
「中型イーターが矢後さん狙ってましたよ。こういう危ないこともあるんで、単独行動はやめてください。矢後さん、ただでさえ死にやすいんだから」
「おー、あぶね」
久森の攻撃の威力が倍近く上がっていると斎樹は感じた。これまでの彼は矢後が仕損じた敵でないとトドメが刺せなかったはずだ。彼の戦闘服も矢後と同じものだ。いつか、神ヶ原に仮縫いを無理やり着せられていたものだ。彼はすごく嫌がっていたが、今は割と馴染んでいる。
「矢後、久森……どうして……」
ラ・クロワのうち、やっと頼城が口を開いた。どうして矢後が生きているのか。その戦闘服は何なのか。訊ねたいことはたくさんあった。
「頼城さん、それに斎樹くんも柊くんもご無事で何よりです。でも、ちょっとイーターの数が多いですね……。説明は後でします」
「ハハッ、ちょっと遊ぶかねぇ!」
最後に見たときの何万倍も元気になっている矢後は目を爛々と輝かせながら、己に迫るイーターを見回す。まさに自分の生きる世界はここだとばかりに。矢後に飛びかかったのは中型や小型のイーターだったが、矢後が大鎌を一閃させるとまるで蒸発したかのように消えた。
「あー、つまんね。俺はもっとでけーやつとやる。久森、雑魚は任せた!」
「はー、絶好調ですね……はいはい、やりますよっ……と!」
大型の方へ向かった矢後を見送りながら、久森はグローブをつけた右手で地面を叩く。久森の背後から迫っていたイーターたちが地面から生えた糸に串刺しにされた。
「丸視えなんだよね……」
そう呟いた彼の目は普段よりずっと明るい色をしていた。糸にやられた中型や小型は霧散したが、久森に大型イーターが迫っていた。
「久森!」
斎樹は思わず叫んだが、久森は狼狽えることなく糸を放った。しかし、致命傷には至らない。普段の彼から考えられない邪悪な顔で舌打ちをした。いつも一緒にいる人間に感化されたのだろうか。
「チッ……矢後さん、仕留め損ないました。後お願いします!」
「しゃーねえな!」
何体もの大型イーターを屠っていた矢後が戻ってきて、久森が対峙していた大型に大鎌を振り下ろす。
ラ・クロワの三人を襲っていた脅威が一体一体、風雲児の二人によって始末されていく。
大方片付いたところで、久森が三人を振り返った。
「お待たせしました。遅くなってすみません。矢後さん、起きるのがホント遅くて……」
「悪りぃなぁ、おいしいとこ全部持って行っちまってよ」
「何故、矢後は生きている? お前は血を吐いて死んだはずだろう」
「勝手に殺すな。うるせー奴に叩き起こされたんだよ」
「まったく、相変わらず頑丈なのか病弱なのか分からん男だ」
相変わらずの二人に安心したのか、頼城の頬が緩む。
「俺も久森が本当に矢後さんを連れてくるとは思わなかった……」
「起こすの、結構苦労したんだよ。お陰で僕はこの人に地獄の底までついていくことになっちゃったんだけど……」
「どういうことだ?」
「三人のためのリンクユニットを持ってきたんだ」
久森が置いていたアタッシュケースを開けて、三人に中を見せる。紫色のリンクユニットが並んでいる。普段と形が違った。
「これはなんだ? 久森」
「強化版のリンクユニットです。より僕たちの能力や合わせて作られていて、普段の戦闘服の倍以上の力を引き出すことができます。途中で会った指揮官さんにも渡したので今頃、本隊の方でも配られていると思います。ラ・クロワの皆さんの分は僕たちが持ってきましたが」
「それを使えば、強くなれるってこと? なら早く……」
「待って、柊くん。使う前に一つ言うことがあるんだ。これは副作用として、すごい中毒性を持っていると神ヶ原さんが言っていました。一度使えば一生これが手放せなくなる……。『普通の人間』には戻れなくなるそうです。だから、よく考えてから使ってください」
そう言った久森の顔は真剣だった。一番『普通の人間』に固執しているのは彼だと思うのだが、その彼が『普通の人間』でいられなくなる上位戦闘服を纏っている。斎樹にはそれが不思議だった。
「じゃあ久森、どうしてお前が?」
「さっき言ったよね? 『僕はこの人に地獄の底までついていくことになっちゃった』って……はあ」
チラ、と暇そうに欠伸をしている矢後を一瞥して、久森はため息を吐いた。久森はそう言っているが、並大抵の覚悟でそんなことはできないだろう。ならば、斎樹もそれ相応の覚悟はせねばならない。だが、もう気持ちは決まっていた。とっくの昔にミュータント手術を受けて人間をやめているようなものなのだ。そんなこと、今更だ。
「で、どーすんの? お前ら。このままここで死ぬか、強くなってこの先に進むか……どっちかだぜ?」
地面に刺した大鎌の柄に寄りかかりながら、矢後が笑う。
「ふん、そんなの、決まっているだろう。愛すべき市民のために人間などやめてやろう!」
「元々、ミュータント化手術を受けて、人間なんてやめているようなものだしな。今更だ」
「……俺は力を得られるならそれでいい」
ラ・クロワの三人もほぼ迷わず、リンクユニットを手に取り、一思いに割った。三人は赤いマントが翻る、貴族のようなラ・クロワの上位戦闘服を纏った。
「へー、やるじゃん」
「ラ・クロワの上位戦闘服、いいなぁ。うちなんて背中にクソダサい刺繍があるのに……」
見ていた風雲児の二人がそれぞれ感想を述べる。久森はやっぱり背中の刺繍が嫌だったらしい。
息を潜めていたイーターたちが再び姿を現わす。だが、まだ終わりは遠いようだ。
「巡、柊、行くぞ! 風雲児にこれ以上遅れを取るわけにはいかないからな!」
「ハハッ、言うねぇ……じゃあ、こっちも行くぞ、久森!」
剣を携え、イーターを見据える頼城。矢後も密かな対抗心があるのか、大鎌の柄を掴むとゆらりと前へ出た。斎樹と久森が心の中でため息を吐くのも構わず、二人はイーターの大群へと飛び込んでいった。
「頼城、迅式のお前が前に出てどうする……まあいい。柊、久森、前に出すぎるなよ!」
「分かった。巡くん、お願い」
「うん、ありがとう、斎樹くん。はー、まったく矢後さんは……。まあ、頼城さんがいるから大丈夫か。僕も視えてるし」
勇ましい上級生にため息を吐きつつ、下級生たちも続いた。
これから先、何が待っているかは分からない。だが、とにかく目の前に立ちふさがる敵を倒し、前に進むことしかできなかった。
190111