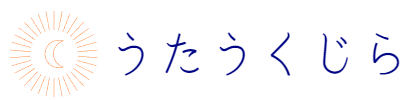自室よりずっと広いリゾートホテルのスイートルーム。調度品はアジアンチックなラタンで居間に置かれたテーブルセットには南国の花が飾られていた。そして、この部屋の担当らしい客室係の手書きメモまで添えられていて、久森は戸惑っていた。なんてクラスの高いホテルなんだ。僕がこんなところにいて、いいのだろうか……と。
この部屋には久森の他、斎樹と御鷹が泊まっていた。二人ともこういうホテルに慣れているようで、至れり尽くせりな部屋の設備を見るたびに戸惑う久森を見て微笑ましげにしていた。やはり、住んでいる世界が違う。
(眠れない)
時刻はすでに午前三時。慣れないホテルに興奮していたのか、久森はまだ眠れずにいた。二時ごろまでは斎樹もラタンのソファに座って本を読んでいたが、布団に入って、ゲームをしている久森に「お前も早く寝ろ」と声をかけてからベッドに入ってしまった。多分御鷹ももう寝ているだろうし、修学旅行で一人だけ眠れていない奴みたいな気分になって、つらい。
必死に目を閉じて、羊の代わりにバケッシュを数えるが脳内がシュッシュ、シュッシュうるさくて、逆に眠れない。うーん、と一人で唸っていると御鷹のベッドの方から布ずれの音がした。
「……御鷹くん?」
「あ、ごめんね、晃人くん。起こしたかな?」
やはり起き上がったのは御鷹だった。身を起こしてそちらを向くとパジャマ姿の御鷹が薄手のパーカーを羽織っていた。
「大丈夫。僕、ずっと起きてたから」
「えっ、眠れないの?」
「うん。ちょっと恥ずかしいけど、興奮してるみたい。寝ようと思って頑張っても眠れないんだよ。もうこのまま起きてようかな……。それで、御鷹くんはどうしたの?」
「俺はちょっと目が覚めちゃった。よかったら、俺も晃人くんの夜更かしに付き合うよ。俺もしばらく眠れそうにないし」
そう言って、御鷹が微笑む。照明は落としているはずなのに御鷹の微笑みが眩しい。久森は思わず手で顔を覆った。
「どうしたの?」
「あ、いつもの発作だから大丈夫……。御鷹くん、眩しくて……」
「発作?!」
御鷹が徳の高いことを言うたびに久森はこうなるのだが、彼はまたか……と思うこともなく、初めて見たかのようにいつも心配してくれる。そういうところもまた優しくて、眩しくて、久森は懲りずに発作を起こしてしまうのだ。
「でも、せっかくだから御鷹くんに付き合ってもらおうかな。飲もうと思って持ってきたんだけど、なかなか暇がなくって」
久森も自分のパーカーを羽織って、ベッドから降りると冷蔵庫を開ける。久森が来てすぐ冷蔵庫に入れておいたもの。それはラムネだった。当然、劇場版カメンジャーズの特典シール付き限定版ラムネである。シールが欲しいあまり、駄菓子屋にあったものを買い占めてきた。荷物持ちに連れてきた矢後はそんな彼を大層呆れた顔で見ていたが、そんなことは知らない。むしろ、運ぶ間に何本か割ってシールを台無しにしたことを悔い改めてほしい。
しかし、運んでくれたことは確かなのでお礼に特典シールを回収した上で何本か矢後にも進呈した。他の人に分けたり、自分で飲んだりしているうちに三本残ったのでせっかくだから三人で飲もうと思って持ってきたのだ。
「ああ、これ……ラムネだね」
「うん。三人で飲もうと思って持ってきたんだ。特典のシールは取っちゃったけど……」
「一時期、光希が気に入ってよく飲んでたよ。飲んだ後のビー玉がきれいだからって」
「じゃあ、洗って明日、光希くんにあげようか」
久森はそのままラムネを開けようとするがそっと御鷹に止められた。
「せっかく海に来たんだし、砂浜で飲まない? 月明かり、結構明るいよ」
くすり、と笑いながら、御鷹が外を指さす。頼城が手配したリゾートホテルのスイートルームは一つ一つの部屋がロッジのように独立している。だから、すぐに海に出ることができた。彼の提案はなかなか魅力的だ。窓から差し込む月明かりが御鷹の後光のように差していて久森は思わず目を覆った。断る理由などなかった。
斎樹を起こさないように部屋から出て、鍵をかけた二人はラムネを片手にビーチサンダルで浜辺を歩いた。夜の海は静かだ。月明かりのおかげでよく見える波は静かに打ち寄せては引いていく。白い砂浜に残っているのは二人の足跡だけでそれも波がどんどん消していく。
「この辺りにしようか」
「うん」
誰かが置き忘れたビーチパラソルを見つけて、その下に座る。改めて空を見上げると本当に月が明るい。周りの星々も負けじと輝いていて、まさに満天の星空という言葉がよく似合う。空に見惚れながら、久森はラムネのパッケージを開いた。フィルムをポケットにしまい、フタを少し強く押し込んだ。瓶の中にビー玉が落ちて、波音にしゅわーっという音が混じる。御鷹も同じようにラムネを開栓していた。
「あっ、こうすると本当にきれいだね」
ラムネの瓶、光希がよくこうしてるんだ。そう言って、御鷹が瓶を月明かりにかざして笑う。久森もそれにならって、瓶を月明かりにかざす。青鈍色をした瓶の中をしゅわしゅわした炭酸の泡が泳ぐ。その向こうにある月が歪んで見えて、まるで瓶の中に閉じ込められてしまったようだ。瓶の中の月はビー玉と共に転がっている。
「ホントだ。きれいだね」
久森もつられて笑う。こんなことに気づくなんて、やっぱり光希は心が美しい。もちろん、その保護者である御鷹も。
瓶の中の景色を楽しんでから、一口ラムネを飲む。口の中にもしゅわしゅわが広がった。すっきりとしたほのかな甘味がおいしい。しかし、瓶の大きさに対して中身はすぐになくなってしまって、空になってしまった。
「なくなっちゃったね」
中のビー玉をカラカラ鳴らしてから、もう一度瓶を月明かりに透かす。もう月は閉じ込められなくなった。なんだか魔法が解けたみたいだ。
「どうしたの?」
「いや、中身があるときは月が閉じ込められてるみたいだなって思ってたんだけど、今見るともうそういうこともなくなっちゃったから、なんだか魔法が解けたみたいだなって……」
久森の話を聞いて、御鷹がくすくすと笑う。
「僕、何か変なこと言ったかな?」
「ごめんね……いや、晃人くん、かわいいこと言うなって思って……」
謝りながらも御鷹はまだ笑っている。久森としては至って真面目に言っただけなのだが、ちょっとだけ心外だ。でも、御鷹が笑ってくれるならそれでいい気もする。言い返す言葉もなく、下を見ると砂の中に青いものが見えた。なんとなく拾ってみるとそれはシーグラスだった。ざらついた感触、波や岩に揉まれて柔らかく丸まったそれを御鷹に見せる。
「シーグラスだね」
「この辺り、結構落ちてるのかな? これも拾って、ビー玉と一緒に光希くんのお土産にしない?」
「ありがとう、きっと光希も喜ぶよ。巡くんもそれでいいかな?」
「うん。でも、呆れられちゃいそうだね」
シーグラスを渡されて、苦笑いを浮かべる斎樹の姿を思い浮かべて、二人で笑う。
二つのラムネの瓶いっぱいにシーグラスを拾って帰る頃には空が白み、朝になっていた。二人の予想通り、斎樹は苦笑いを浮かべて二人を待っていた。
END