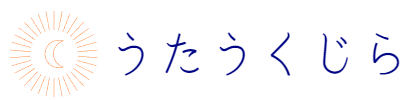191221公開
伊勢崎と初めて出会った指揮官見習いの花田の話
これまで、三十年近く働いてきた会社を早期退職して、花田誠二は転職先にALIVEを選んだ。指揮官適性があるから、と花田をヘッドハンティングしたのはALIVEである。
三十年働いてきた職場に未練はない。仲良くなった同僚もいないし、仕事内容もやりがいがあるものではなかった。ただ、給料がもらえるから働いている。それだけだ。
恋人もいないし、結婚もしていない。ただ、実家で暮らしている親が年老いていくだけだ。一人で二人も介護する気力はないので、介護施設に入ってもらうしかない。そのためにはお金がいる。指揮官になれば、これまでの倍は給料を出すと言ったので、縹はそれに乗ることにした。
「まあ、仕事は簡単ですよ。ヒーローの高校生に指示を出したり、イーターの観測をしたり、大規模討伐の作戦を立てたりするだけです」
花田の指導係に抜擢された萌黄要という三十路前の青年は何でもないことのように言った。関西訛りのそれを聞きながら、その内容、かなり難しいのでは、と思った。
「まあ、それが責任重大なんですけどねえ。あ、でもあいつらともみくちゃになってごはん食べたり、遊んだりするのは楽しいですよ」
「萌黄くん、君の歳ではそうだろうね……でも、私はもう五十路を過ぎてるんだ」
二十代、三十代くらいならまだなんとか十代についていけるだろう。しかし、花田はすでに五十代である。とてもついていける気がしない。きっと、ここでも馴染めず、前の職場のように過ごすだけなのだろう。
「まー、花田さんもすぐ馴染みますよ! あ、ここが合宿施設です。いつも五人の特訓メンバーが詰めています。今日は誰やったかなあ」
萌黄はあー忘れたわ、などと言いながら明るい髪色の頭を掻いた。指揮官のくせにずいぶんとぼけたことを言う。大丈夫なのだろうか、この男。
合宿施設自体はきれいだ。二階建ての施設だが、寮のような趣がある。門をくぐるとすぐ、脇の芝生で少年が一人寝転んでいた。砂色の髪に黒いヘアバンドを着けた彼はずいぶん派手な刺繍が入った学生服をだらしなく身につけている。これは俗に言う、ヤンキーという奴ではないだろうか。これまで事なかれ主義で生きてきた花田としてはあまりお近づきになりたくない。
「あー、矢後がおったな」
野良猫でも見つけたかのようなノリでそう言うとそのまま、萌黄は進んでいく。
「彼は起こさなくてもいいのかい?」
「大丈夫ですよ。あいつはいっつもその辺で寝てますから」
「そういうものなのか……」
玄関に辿り着いて、萌黄がガラス戸を開ける。玄関では金髪の少年が白いシャツとチェックのスラックスを泥で汚しながら何かを丸めている。泥団子だろうか。
「あ! 萌黄さん、こんちわ!」
萌黄の存在に気づいた彼は顔を上げて、ニカッと笑った。彼が笑うだけでパッと周囲が明るくなった。そんな気がする。
そして何より彼の輝くような金髪と美しい顔の造形だ。こんなに美しい人間を花田はこれまでの人生で見たことがない。ついつい見入ってしまった。
「おー、伊勢崎やん! うわ、何作ってんのん?」
「泥団子! 最近ハマってんの」
「お前、どろどろやんけ……。また志藤に怒られんで」
「今週は正義いないからだいじょーぶ! きれいに作れたら評価してよ!」
「いや、何をどう見たらええねんそんなん」
「ん? 後ろの人は?」
怪訝そうに首を傾げ、少年……伊勢崎が萌黄に訊ねる。
「あー、今日から研修に入る指揮官見習いさん、いうとこかな。ワシと一緒に仕事するからよろしく頼むわ。花田さん?」
萌黄に視線を向けられて花田はやっと正気に返る。
「あ、ああ……花田誠二だ。今日からよろしく。えーと……」
「オレ、伊勢崎敬っていうんだ。よろしく、ハナダさん!」
ニカッとまたひまわりのような笑顔を浮かべると伊勢崎が手を差し伸べてくる。花田はそれを握り返すと自然と微笑んだ。
「ああ、よろしく……敬くん」
この職場では人間関係もうまくいきそうな気がする。伊勢崎の笑顔を見ながら、花田はそう思った。
191221